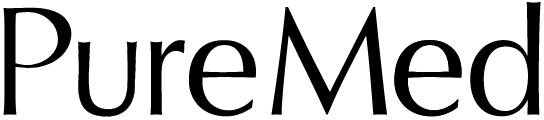ミネラルとは?ミネラルが多い食べ物と効率よく摂取する方法

ミネラルは、健康をサポートする5大栄養素の1つです。ミネラルが体に必要な栄養素であることはわかるものの、どんな働きをしているのかはよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、ミネラルとは何か、どんな食品に多く含まれているのか、そして効率よく摂取するためのポイントについて、わかりやすく解説します。
ミネラルとは?
ミネラルとは、人間の健康維持に欠かせない微量金属のことで、5大栄養素のうちの1つとされています。
体内では作り出すことができないため、食事からの摂取が必要です。
ミネラルは、主に骨・歯の形成や、体内の水分バランスの調整、酵素の働きを助けるなど、さまざまな役割があります。ミネラルが不足すると、体の不調につながるおそれもあるため、栄養バランスの良い食生活を心がけて、しっかりと補給することが大切です。
ミネラルの種類と主な働き

体内に必要となるミネラルのことを「必須ミネラル」といいます。
この必須ミネラルは、多量ミネラルと微量ミネラルに分けられます。
ここでは、多量ミネラルと微量ミネラルをそれぞれ解説します。
多量ミネラル

多量ミネラルとは、1日の推奨量や目安量が100mg以上必要なミネラルを指します。
この多量ミネラルは5種類あります。
・ナトリウム
体内の水分バランスを維持するミネラルです。
pHの調整や筋肉の収縮、神経の情報伝達などに関与しているミネラルでもあります。体内には、0.1~0.2%存在していて、細胞外液に多く含まれています。
体内に必要なミネラルですが、過剰摂取すると、むくみの原因や血圧の上昇などのリスクにつながるおそれがあるため注意しなければなりません。
・カリウム
血圧を調整したりむくみを防いだりするミネラルです。
体内には、100~150g含まれていて、ほとんどが細胞内の体液にあるとされています。
また、筋肉や神経への伝達にも関わりのあるミネラルです。
カリウムは、食事をしっかりととっていれば不足することはないといわれています。
・カルシウム
カルシウムは、骨・歯を丈夫にするミネラルで、体内で最も多く存在しています。
ほとんどが骨や歯のエナメル質に存在していて、骨や歯を形成している成分です。
また、1%ほどは血液や筋肉、神経に存在していて、血液の凝固を施して出血を防いだり神経の興奮を抑えて精神の安定を保ったりなど、重要な働きをしています。
カルシウムが不足すると骨軟化症や骨粗鬆症などになる可能性があります。
・マグネシウム
マグネシウムは、カルシウムやリンと同じく歯や骨を形成するミネラルの1つです。
それ以外にも、多くの酵素の働きを助ける補因子として働きます。
エネルギー生成や代謝などに関与している重要なミネラルともいえます。
マグネシウムが不足すると吐き気、嘔吐、眠気など低マグネシウム血症を起こす可能性があります。
・リン
リンは、体重の約1%を占めるミネラルです。体内に存在するほとんどが、リン酸カルシウムやリン酸マグネシウムとして、骨や歯に含まれており、残りのリンは軟組織や細胞膜、細胞外液などに含まれています。
リンはエネルギー生成にも関わりがあることから、生命を維持するために必要な成分です。
さまざまな食品に含まれているため、バランスのとれた食事をしていれば不足するリスクはありませんが、過剰摂取するとカルシウムの吸収を妨げるほか、心血管疾患病のリスクがあるため注意が必要です。
参考文献:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
微量ミネラル

微量ミネラルとは、1日の推奨量や目安量が100mg未満のミネラルを指します。
日本人の食事摂取基準では、8種類の微量ミネラルの摂取が推奨されています。
・鉄
血液の成分であるヘモグロビンや酵素の構成成分です。
全身に酸素を運ぶ役割があるミネラルで、鉄が不足すると貧血を引き起こします。
不足しやすいミネラルのため、意識的に摂取しましょう。
特に女性は、月経や妊娠などの影響で貧血になりやすいため注意が必要です。
・亜鉛
亜鉛は、全身のさまざまな臓器に存在していて、生命活動をサポートするミネラルです。
新しい細胞の生成や免疫機能の維持、さらに味覚を感じるための味蕾細胞にも関与しているといわれています。
そのため、亜鉛が不足すると味覚障害や食欲不振などが起こる可能性があります。
・銅
銅は、体内では鉄の吸収を助け、血液の形成に関与しています。
ほかにもエネルギー生成や活性酸素の除去、神経伝達物質の生成などを助けているミネラルです。銅は血液の形成に関与していることから、不足すると貧血につながるおそれがあります。
・マンガン
金属酵素の構成成分の1つです。骨にも25%含まれていることから、骨の発達に関わっています。
残りは、体内のさまざまな組織や臓器に分布していて、酵素を活性化させることもあるといわれています。
・ヨウ素
ヨウ素は、体内の甲状腺に70~80%存在し、甲状腺ホルモンをつくるのに必要なミネラルです。
ヨウ素が不足すると、甲状腺肥大を引き起こす可能性があります。
わかめや昆布、海苔などの海藻に多く含まれ、日本人は定期的に摂取していることから、不足するおそれはないといわれています。
・セレン
セレンは、抗酸化システムや甲状腺ホルモン代謝において重要な役割を持っているミネラルです。
酵素の生成にも関わりを持ちます。
セレンの不足は心筋症や不整脈、貧血などの原因になるといわれています。
・クロム
クロムは、体内で糖代謝や脂質代謝の維持に関与している微量ミネラルです。体内に存在するクロムは微量ですが、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの作用に重要な役割を果たしています。クロムは、偏った食生活をしていなければ不足することはないとされています。
・モリブデン
モリブデンと聞くと金属をイメージするかもしれませんが、体内でも欠かせないミネラルの1つです。
モリブデンは酵素の構成成分の1つで、肝臓や腎臓に存在しており、糖質や脂質の代謝を助ける役割を持ちます。
モリブデンは、きちんと食事をとっていれば不足することはないといわれています。
参考文献:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2025年版)」
ミネラルが多い食べ物とは 
ミネラルはどの食べ物に多く含まれているのでしょうか。
ここでは、ミネラルの種類ごとに、多く含む食品をご紹介します。
多量ミネラルを多く含む食品
|
ナトリウム |
しょうゆ、味噌 |
|
カリウム |
アボカド、バナナ |
|
カルシウム |
乾燥エビ、しらす、おじゃこ |
|
マグネシウム |
ひじき、アーモンド、枝豆 |
|
リン |
しらす干し、ロースハム |
さまざまな食材から多量ミネラルを摂取することができます。
基本的には、栄養バランスの整った食事をすることで、十分なミネラルをとることが可能です。
微量ミネラルを多く含む食品
|
鉄 |
レバー、ひじき、ほうれん草、あさり |
|
亜鉛 |
牡蠣、牛もも肉 |
|
銅 |
レバー、魚介類 |
|
マンガン |
ごま、玄米 |
|
ヨウ素 |
海藻類、いわし |
|
セレン |
ホタテ、かつお節 |
|
クロム |
青のり、ひじき |
|
モリブデン |
落花生、焼きのり |
微量ミネラルのなかでも、鉄は不足しやすい成分です。
特に貧血気味である方は、レバーやひじき、ほうれん草などを食事にとり入れて、鉄を摂取するよう心がけましょう。
ミネラルを効率よく摂取する方法

ミネラルは体の機能をスムーズに保つために欠かせない栄養素ですが、体内では合成できないため、日々の食事から意識的にとり入れることが大切です。ここでは、ミネラルを効率よく摂取するための工夫をご紹介します。
ミネラルの吸収を助ける栄養素と組み合わせる
ミネラルの吸収率を高めるには、相性の良い栄養素と一緒に摂取することがポイントです。
カルシウムはビタミンDと組み合わせることで腸での吸収が促進され、骨や歯の形成をしっかりサポートしてくれます。
また、鉄分はビタミンCと一緒に摂取することで吸収効率がぐんとアップします。
例えば、鉄分が豊富なレバーやほうれん草に、ビタミンCが豊富なじゃがいもやピーマン、トマトなどの食品を合わせると良いでしょう。
料理にプラスしてミネラルアップ

普段の料理にミネラルを豊富に含む食材をプラスするのも、手軽に摂取量を増やすコツです。
例えば、おにぎりに昆布やわかめ、ちりめんじゃこを加えることで、風味も栄養価もアップします。
また、サラダに海藻やナッツをトッピングすれば、ミネラルだけでなくビタミンCや食物繊維も一緒に摂取でき、栄養バランスが良くなります。
バランスの良い食事を心がけた上で、足りない分はサプリメントで補うのも良いでしょう。
ただし、ミネラルの過剰摂取は健康に影響を及ぼす可能性があるため、調整も忘れずに行いましょう。
まとめ
今回は、体内に必要なミネラルについて解説しました。
ミネラルは、人間の健康維持に欠かせない微量金属のことで、5大栄養素のうちの1つです。
栄養バランスの整った食事を心がけていれば、ミネラルが不足することはありません。
気になる場合は、過剰摂取に気をつけつつ、不足分をサプリメントや健康食品などで補うのも良いでしょう。