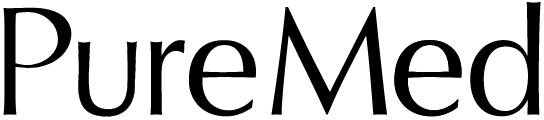運動不足が免疫力低下につながる?その理由と免疫力向上につながる運動
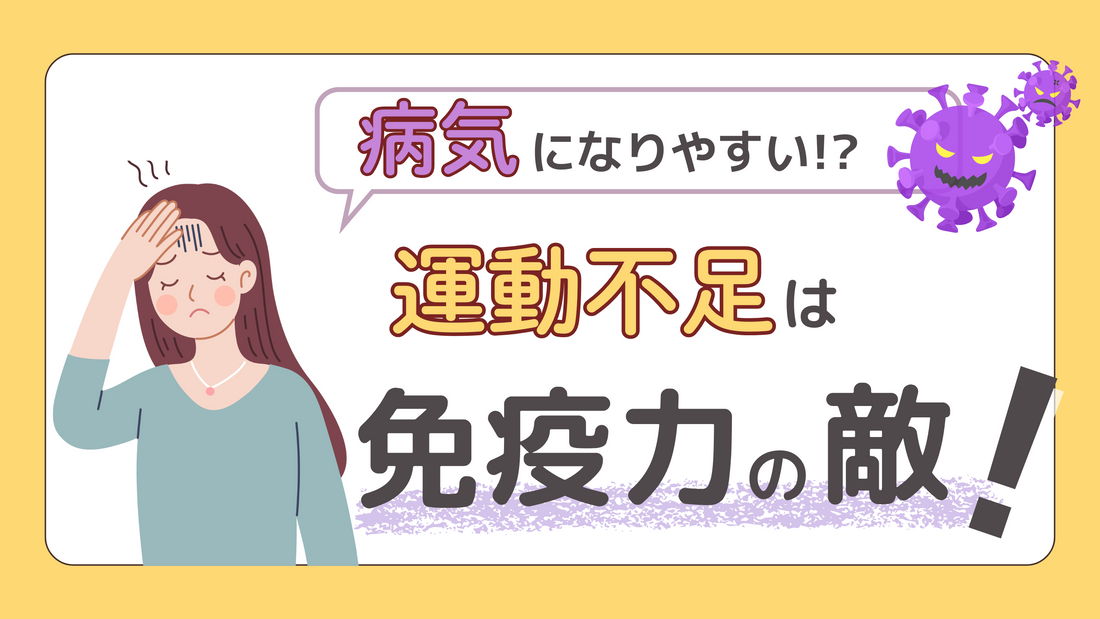

忙しい生活のなか、運動不足が気になっているという方は多いのではないでしょうか。運動不足になると、免疫力の低下につながることがあります。適度な運動は血流を促進し、免疫細胞の活性化につながるため、免疫力を上げるには体を動かすことが重要です。
今回は、運動不足が免疫力に与える影響や、免疫力向上に効果的な運動方法について解説します。
そもそも免疫力とは?
免疫力とは、体内に入ってきたウイルスや細菌、病原体などの異物を排除し、感染症や病気から体を守るための力のことを指します。
体の中に存在するさまざまな免疫細胞が免疫の機能を担っており、免疫細胞が活性化することで、ウイルスや細菌、病原体から体を守っています。ただし、免疫力はストレスや生活習慣の乱れなどにより低下するおそれがあります。
免疫力低下によるリスク
免疫力が低下すると、ウイルスや細菌、病原体への抵抗力が弱まり、風邪や感染症にかかりやすくなるのです。
病気にかかりやすくなるだけでなく、重症化や治りにくくなる可能性もあります。
健康を維持するためには、免疫力が低下しないよう心がける必要があります。
免疫力を上げるために重要なのは、免疫のバランス力
風邪や感染症といった病気から体を守る免疫。
実は、免疫力は高すぎても良いというわけではありません。
免疫反応が高まりすぎるとアレルギーや自己免疫疾患などの原因になる可能性もあるため、適度な状態が良いとされています。
また、世間一般で使われている免疫力を上げる・高めるというのは、「免疫のバランス力を上げる」という意味で使用されています。
免疫反応を強くしようという意味ではなく、あくまでも健康的な体を保つための言葉として使われています。
運動不足は、免疫力の低下につながる?

運動をすることで、免疫細胞が活性化するといわれています。
免疫細胞が活性化すると免疫力が向上し、体外から侵入してきたウイルスや病原菌から体を守ることにつながります。
逆に運動不足の状態が続くと、代謝の低下や血行不良、体温の低下などを引き起こし、免疫細胞が活性化しなくなってしまいます。
疲れやすくなり、風邪や病気などを繰り返してしまう可能性があるのです。
激しい運動を高頻度で行うのは逆効果
運動をするのは健康を保つために大事なことですが、激しい運動には注意が必要です。アスリートのような激しい運動を高頻度で行うことは、逆に免疫力を下げるとされています。
実際に、激しいトレーニングを行うスポーツアスリートは免疫力が低いことがわかっています。
運動するのが望ましいとはいえ、アスリートのような運動をとり入れる必要はなく「適度な運動」に留めるのが適切です。
免疫力の向上につながる「適度な運動」の目安
厚生労働省が公表している「健康づくりのための身体活動基準2023」では、身体活動や運動についての目安が公表されています。
ここでは、「健康づくりのための身体活動基準2023」を元に、適度な運動の種類・運動量についてわかりやすく解説します。
健康的な成人の場合
健康的な成人であれば「毎日60分以上の積極的な運動」と「息が弾み汗をかく程度以上の運動を週60分以上」「筋力トレーニングを週に2~3回」を行うことが推奨されています。
毎日60分以上、積極的に体を動かす
まず、健康的な成人であれば「歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分以上行う」ことが推奨されています。
これは、歩行でいうと1日8,000歩以上に相当するとされています。
歩行以外にも、掃除機をかけたり風呂掃除をしたりといった生活活動(日常生活における活発な動き)でも良いとされています。
単純に1日8,000歩以上散歩するのも良いですし、散歩を30分する+家の掃除を30分行うのも適度な運動に当てはまります。
座りっぱなしにならずに、積極的に体を動かすことを意識することが大切です。
以下が推奨されている生活活動の例です。
これらの生活活動や運動を組み合わせて、1日60分以上行うことを意識しましょう。
出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2023」を元に作成
息が弾み汗をかく程度以上の運動を週60分以上行う
次に、「息が弾み汗をかく程度以上の運動を週60分以上行うこと」が推奨されています。
これは、体操や筋力トレーニングなど手軽にできる運動や、卓球、テニスなどのスポーツが当てはまります。
特に筋トレは、生活機能の維持・向上だけでなく、疾患発症予防や死亡リスクの軽減にもつながると考えられているため「週に2~3回行うこと」が推奨されています。
週に2~3回、60分以上筋トレやランニングなど体を動かす運動をとり入れるのが理想的です。

出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2023」を元に作成
慢性疾患(高血圧、2型糖尿病、脂質異常症、変形性膝関節症)を持っている場合
高血圧や2型糖尿病、脂質異常症、変形性膝関節症といった慢性疾患を持っている場合、体が動かせる状況であれば、運動をとり入れることが推奨されています。
ただし、身体状況によっては、運動が推奨されていないケースもあるため必ず医師に相談したうえで運動をするようにしましょう。
糖尿病の場合は、インスリン抵抗性の改善を期待して、運動しない日が2日以上続かないよう推奨されています。
高血圧症の場合は、運動による急性効果の持続時間がほぼ一日といわれていることから、運動はなるべく毎日行うことが望ましいとされています。
具体的には、健康な成人と同じく「歩行またはそれと同等以上の強度の身体活動を1日60分以上行うこと」が推奨されています。
1日30分以上、意識して体を動かすことと、それ以外の生活活動を行うことで、推奨値である毎日60分以上の運動となります。
例えば、ランニングを30分行い、掃除をかけたりフロア掃きをしたりなどの生活活動を行うといった方法があります。
以下の表の「活発な生活活動の例」と「活発な運動の例」をうまく組み合わせて、体を動かしましょう。
ただし、高齢者や体力レベルが低い場合は合計して40分(1日6000歩相当)が推奨されています。
また、筋力トレーニングを週2~3日行うことが推奨されています。
筋力トレーニングのかわりに、水泳などの活発な運動をとり入れても問題ありません。

出典:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2023」を元に作成
参考文献:厚生労働省「健康づくりのための身体活動基準2023」
適度な運動には、さまざまな効果が期待できる

適度な運動を習慣化させることは、免疫力の維持だけでなく、生活習慣病の予防やストレス解消の効果も期待できます。
生活習慣病の予防につながる
運動不足の状態が続くと、食べすぎによる肥満、糖尿病、高血圧などの生活習慣病を引き起こしやすくなります。
定期的な運動習慣は、エネルギー代謝を高め、肥満を予防します。
さらに、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の発生を抑える効果も期待できます。
ストレス解消につながる
適度な運動には、メンタルケアの効果も期待できます。
ストレスがたまると、やる気が出ない、気分が落ち込むといった精神症状や疲労感、頭痛、めまいといった身体症状を引き起こすことがあります。
体を動かすことで気分転換や達成感を味わうことができ、ストレス発散や精神面での充実につながります。
ストレスを感じているときには、自分が楽しいと思える運動をとり入れるのもおすすめです。
参考文献:厚生労働省「身体活動・運動」
まとめ
運動不足が続くと、免疫細胞が活性化せず、免疫力の低下につながり、免疫力が低下することで、風邪や感染症にかかりやすくなってしまいます。
免疫力をキープするには、散歩したり積極的に階段を使ったりして、生活に「適度な運動」をとり入れると良いでしょう。
無理のない程度に日々体を動かすようにして、健康な体づくりを心がけましょう。
|
監修:松永 敦 大北メディカルクリニック 院長
昭和62年関西医科大学卒業。 大阪大学耳鼻咽喉科にて研修後、東京大学音声言語医学研究施設にて文部教官として喉頭生理学を研究。 その後、大阪大学に戻り音声機能外科を臨床面で進める。
36歳で癌を再発したが、自身で考えたサプリメントなどを用いた食事療法により寛解。
現在は大北メディカルクリニック院長として音声を中心とした地域医療に従事。 国内外の患者は60万人超え。
|